宗像大社 沖津宮(おきつぐう)は、福岡県宗像市の沖合約60km、玄界灘に浮かぶ孤島「沖ノ島」に鎮座する神社で、宗像大社三宮の一つに数えられます。ここには宗像三女神の長女である多紀理比売命(たぎりひめのみこと)が祀られ、古代より「海の正三角形」を構成する最も神秘的な聖域として篤い信仰を集めてきました。
沖ノ島は周囲約4km、標高約240mの小さな島ですが、古来より「神宿る島」として扱われてきました。島全体がご神体とされ、一般人の立ち入りは厳しく制限されてきました。上陸できるのは限られた神職のみであり、参拝者や観光客は通常立ち入ることができません。これは「一木一草たりとも持ち出してはならない」「島で見聞きしたことは口外してはならない」といった厳しい禁忌(しきたり)が千年以上守られてきたためであり、その神聖さは現代に至るまで色濃く受け継がれています。
沖津宮が特に重要視されるのは、古代祭祀の遺跡が数多く残されているからです。4世紀から9世紀にかけて行われた国家的な祭祀の痕跡が島内に点在し、発見された奉献品は8万点以上にのぼります。その中には金銅製龍頭、鏡、武具、勾玉、ガラス製品、さらには朝鮮半島や中国との交流を示す遺物などが含まれています。これらの出土品は全て国宝に指定されており、「海の正倉院」とも呼ばれる貴重な文化財群を形成しています。これらは単なる祭具ではなく、古代日本が国の安寧と航海安全を祈願し、大陸との交流を国家事業として位置づけていた証ともいえます。
沖ノ島における祭祀は、航海に出る前に神々の加護を願う重要な儀式でした。遣隋使や遣唐使など、大陸との往来の際には必ず沖ノ島で祭祀が行われ、船団の安全が祈られました。そのため沖津宮は、古代日本の国際交流と外交の要を担った「海の祈りの拠点」でもあったのです。
現代においても、沖津宮は一般の参拝が許されないため、宗像市大島の中津宮や宗像市田島の辺津宮で「遥拝(ようはい)」するのが通例です。特に大島の御嶽山展望台からは沖ノ島を遠望でき、古代の人々が同じように神々へ祈りを捧げたであろう光景を偲ぶことができます。辺津宮には「第二宮」「第三宮」が設けられ、それぞれ沖津宮と中津宮の遥拝所として整えられています。
沖ノ島とその祭祀遺跡の価値は世界的にも高く評価され、2017年には「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。登録理由は「古代から連綿と続く自然崇拝と祭祀の形が、ほぼ完全な姿で残されている」という点にあり、世界的にも希少な宗教文化の証しとして認められたのです。
今日において沖津宮は、航海安全、海上守護の神としてだけでなく、人生の道を切り開く守護神として多くの人々に信仰されています。直接参拝することはできなくても、宗像大社の他の宮を訪れることで沖津宮の神徳に触れることができ、古代から続く「海を渡る祈り」に心を重ねることができます。
総じて、宗像大社 沖津宮は、日本の古代信仰と海洋文化を象徴する神聖な地であり、その歴史的・宗教的価値は極めて高いといえます。一般には足を踏み入れることのできない禁忌の島でありながら、遥拝を通じてその神威は今も人々の心に息づいています。

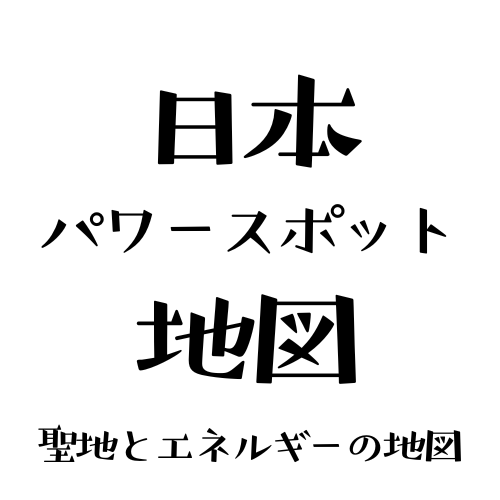
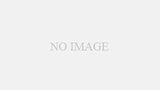

コメントはまだありません。