出雲大社は島根県出雲市に鎮座する、日本を代表する古社のひとつであり、縁結びの神として広く信仰を集めています。正式名称は「いづもおおやしろ」と読み、古くから「大社(たいしゃ)」と呼ばれて親しまれてきました。主祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)で、『古事記』や『日本書紀』に登場する国造りの神として知られています。大国主大神は、国土経営を行った後に天照大神へ国を譲った神であり、その後、幽界(黄泉や神々の住まう世界)を統べる存在としても位置づけられています。また、人と人との良縁を結び、人生の幸福を導く神として厚く信仰され、現在では「縁結びの聖地」として全国から参拝者が訪れています。
出雲大社の創建は明確には定まっていませんが、神話時代にまで遡るとされ、日本最古の神社のひとつに数えられています。『古事記』や『出雲国風土記』などの文献には、大国主大神が国を譲った後に、その功績を称えて壮大な御殿を築いたと記されており、これが出雲大社の起源とされています。平安時代には朝廷から「杵築大社(きづきのおおやしろ)」と呼ばれ、国家的にも重要な神社として崇敬を受けてきました。
出雲大社の本殿は、現在のものは江戸時代の1744年に建立された国宝建築で、高さ24メートルを誇ります。しかし、古代には現在よりもはるかに巨大な社殿が建っていたと伝えられています。平安時代の記録には、出雲大社の本殿は約48メートルに達していたとされ、当時の世界的にも類を見ない木造建築でした。その壮大さを裏付けるように、2000年には直径1メートルを超える巨大な柱が3本組で出土し、古代社殿の存在を証明する重要な資料となっています。
境内に足を踏み入れると、まず目を引くのが神楽殿の巨大なしめ縄です。長さ約13メートル、重さ5トンを超えるこのしめ縄は日本最大級とされ、参拝者に強い印象を与えます。参拝作法も独特で、通常の神社では「二拝二拍手一拝」ですが、出雲大社では「二拝四拍手一拝」を行います。これは大国主大神への特別な敬意を示すものとされ、出雲大社独自の伝統として受け継がれています。
また、出雲大社は「神在月(かみありづき)」の神話で特に有名です。旧暦10月、全国の八百万の神々が出雲に集まり、人々の縁や運命について話し合うとされるため、他の地域では「神無月」と呼ぶのに対し、出雲地方だけは「神在月」と呼びます。この時期には「神在祭(かみありさい)」が執り行われ、全国から多くの参拝者が訪れます。
出雲大社は縁結びの象徴として若い世代からも人気を集める一方、古代から続く日本神話と深く結びついた聖地でもあります。広大な境内、荘厳な本殿、歴史を物語る伝承の数々は、訪れる人々に神秘的な感覚を呼び覚まし、日本の信仰の原点を感じさせてくれる場所といえるでしょう。

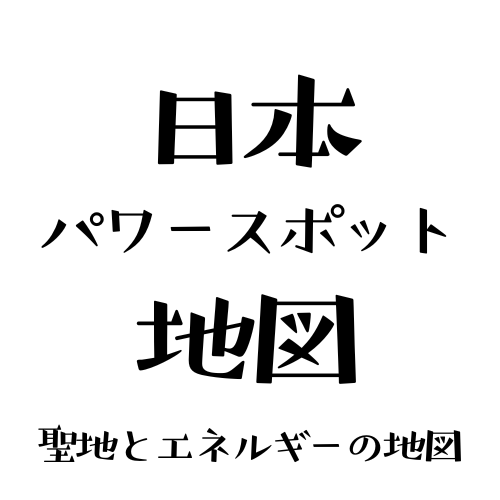
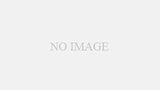

コメントはまだありません。