豊受大神宮(とようけだいじんぐう)、通称「外宮(げくう)」は、三重県伊勢市に鎮座する伊勢神宮を構成する中心的な神社の一つです。内宮(ないくう)で祀られる天照大御神(あまてらすおおみかみ)に対して、外宮では豊受大御神(とようけのおおみかみ)が御祭神として祀られています。伊勢神宮全体は125の宮社から成りますが、そのうち最も重要なのが内宮と外宮であり、両宮を合わせて「神宮」と呼びます。
豊受大御神は、衣食住をはじめとする産業全般を司る神とされ、特に「食」の神として知られます。日本神話によれば、天照大御神が伊勢に鎮まられた後、その御饌(食事)を司る神を必要とされたため、第21代雄略天皇の勅命により、丹波国(現在の京都府北部)から伊勢へ遷されました。以降、豊受大御神は天照大御神の「御饌都神(みけつかみ)」として、日々の食事をはじめとする生活の根源を支える役割を担っています。
外宮の境内は内宮と同じく広大で、正宮(しょうぐう)を中心に多くの別宮や摂社が鎮座しています。正宮は唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)と呼ばれる古代的な建築様式で建てられており、檜の素木造りで荘厳かつ簡素な美しさをたたえています。参道を進むと豊かな杜(もり)が広がり、凛とした空気の中に神域としての厳粛さを感じることができます。
外宮の最大の特徴の一つに「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうのおおみけさい)」があります。これは毎日朝と夕の二度、豊受大御神を通して天照大御神に食事を供える祭典で、途切れることなく連綿と続けられています。神々に食を捧げるこの祭りは、生命の営みを支える食の大切さを象徴しており、外宮の役割をもっともよく表す儀式といえるでしょう。
さらに、外宮と内宮の参拝順序にも伝統があります。古来より「外宮先祭(げくうせんさい)」と呼ばれ、参拝する際は外宮を先に、内宮を後にお参りするのが正式な作法とされています。これは、まず食を司る豊受大御神に感謝を捧げ、その後に太陽神である天照大御神を拝するという生活の根源を重んじる日本人の精神を表しています。
外宮にも式年遷宮が行われます。20年ごとに社殿を建て替え、神宝や御装束を新調するこの大祭は、内宮と同様に1300年以上続く伝統行事です。遷宮は単なる建築の更新ではなく、伝統技術や信仰を次世代に継承する重要な儀式でもあります。
また、外宮の神域には正宮のほかに多くの別宮があり、その中でも「多賀宮(たかのみや)」は特に有名です。豊受大御神の荒御魂(あらみたま)を祀る別宮で、個人的なお願い事をする際には多賀宮を参拝するのが古くからの習わしです。これに対して正宮では、個人的な願望ではなく日常への感謝を伝えるのが本来の参拝の姿とされています。
さらに外宮の境内には「風宮(かぜのみや)」「土宮(つちのみや)」など自然と密接に関わる神々を祀る別宮もあります。風や土といった自然現象が古代の人々の生活に直結していたことを考えれば、これらの社の存在は外宮が「生活を支える神々の総本宮」であることを象徴しているといえるでしょう。
総じて、豊受大神宮(外宮)は「食と産業の守護神」を祀る聖地であり、内宮と一体となって日本人の精神的基盤を形づくっています。外宮に参拝することは、私たちが生きるうえで欠かすことのできない衣食住や自然の恵みに感謝し、日常生活そのものを神聖なものとして見つめ直す機会となります。伊勢神宮を訪れる際には、外宮から参拝を始めることによって、日本文化が重んじてきた「食」と「命の循環」への深い祈りを実感できるでしょう。

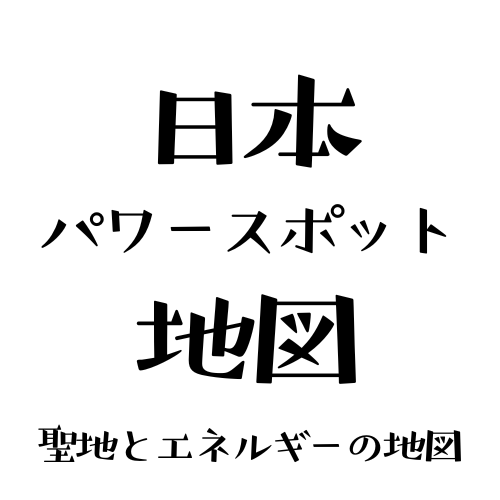
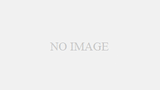

コメントはまだありません。