天岩戸神社は、宮崎県西臼杵郡高千穂町に鎮座する古社で、日本神話「天岩戸伝説」の舞台として知られています。主祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)で、社名の由来である「天岩戸(あまのいわと)」は、古事記や日本書紀に記される有名な神話に登場する洞窟のことを指します。
伝承によれば、天照大御神は弟である須佐之男命(すさのおのみこと)の乱暴に心を痛め、天岩戸に身を隠してしまいました。太陽神である天照大御神が姿を隠すと世界は暗闇に覆われ、災いが広がります。そこで八百万の神々が集まり、祭りや舞を奉じて天照大御神を誘い出しました。そのとき、天宇受売命(あめのうずめのみこと)が岩戸の前で舞を舞い、神々が大笑いしたことで天照大御神が岩戸を少し開け、力自慢の天手力男命(たぢからおのみこと)が岩戸をこじ開けて外に出したとされています。この出来事が「天岩戸神話」と呼ばれ、日本の神話の中でも特に象徴的な場面となっています。
天岩戸神社は、この伝説の「天岩戸」を御神体として祀っています。境内には「西本宮」と「東本宮」があり、西本宮では天照大御神を祀り、東本宮では岩戸を出た後の天照大御神を祀っています。また、神職の案内を受けることで「天岩戸」を実際に遥拝できる特別な場も用意されており、参拝者にとっては神話の舞台を直に感じられる貴重な体験となります。
さらに、神社から徒歩圏内にある「天安河原(あまのやすがわら)」も見どころです。ここは八百万の神々が集まり、天照大御神を岩戸から出す方法を相談したと伝えられる場所です。河原一帯には無数の石が積み上げられており、訪れる人々が祈りを込めて石を積む光景が広がります。洞窟の奥には天安河原宮があり、神秘的な雰囲気が漂う聖地として知られています。
天岩戸神社の歴史は古く、創建年代は定かではないものの、『延喜式神名帳』にも名が記される式内社として由緒ある神社に数えられています。境内には杉や楠などの巨木が立ち並び、神域ならではの厳かな空気に包まれています。特に、天照大御神の神話と直結するため、全国の神社の中でも「神話のふるさと」を象徴する存在として高い霊的価値を持っています。
参拝者は太陽の神を祀るこの神社で「開運」「再生」「光を取り戻す」といった御利益を願います。暗闇から光を取り戻す神話のエピソードは、困難を乗り越える力や人生の転機を示す象徴ともされ、多くの人々に勇気を与えてきました。
天岩戸神社は、単なる観光地ではなく、日本神話が今なお生き続ける聖地です。伝説の舞台に身を置くと、古代から続く信仰の深さを実感でき、訪れる人々は自らの人生に光を招き入れるような特別な感覚を覚えることでしょう。

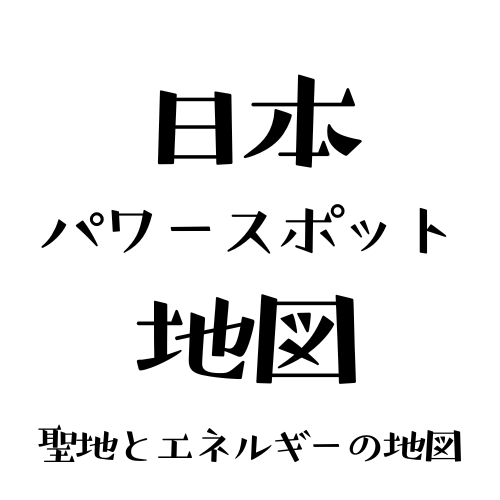
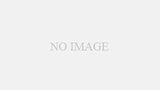

コメントはまだありません。